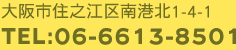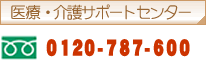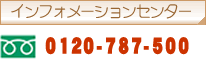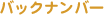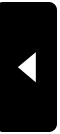看取りの基本
2021年01月21日
看取りの基本
みなさまこんにちは、12月はとても勉強会が多くて毎日ブログ記事の更新作業に追われている ぼくです。
さて今回は、令和2年12月17日に看護師を講師に迎えまして看取りケアについて教えてもらいました。
みなさまも「看取りケア」って何?と思われているでしょうが
看取りケアとは
「近い将来死が避けられないとされた利用者様に対して、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和、軽減するとともに人生の最後まで尊厳ある生活を支援する事」
簡単に言いますと「本人らしさを失わず、穏やかに最後の日を迎える」ことです。
看取りケアの中でも、ターミナルケア・ホスピス(緩和ケア)といくつかのケアがありまして
言葉だけならご存じの方もおられると思います。
ターミナルケアとは、終末医療(苦痛緩和・最後を看取る)
ホスピスとは、不治の病(ガン・エイズ等)の終末医療(苦痛緩和・最後を看取る)
また、看取りケアは、在宅や介護施設で行う身体的ケア
ターミナルやホスピスは、病院で行う医療的ケアとしています。
‶食べる„行為について少しお話します。
私たちは「生きるため」体の機能維持のために食事を摂ります。
終末期を迎える高齢者の方は、食欲が減少していきますが、それは体が自然にそうなってくるそうです。
次の段階へ体が以降すると、体内の水分を減らしていき体が楽に最後を迎えられるように
わざと脱水症状になっていきます。
そして、最後を迎える時期が近づくと、眠る時間が長くなり残りの生命をゆっくりと使い切って最後を迎えます。
このように、人の身体も死を迎え入れる準備をしていきます。
ここ雅秀苑では、看取りへと移行するための指標がありそれに準じて看取りの対応を実施しています。
では、雅秀苑の看取り指標を少しご紹介します。
~ステージ1~ 死の3か月から1か月の特徴
・興味がなくなる、眠る時間、まぶたを閉じる時間が長くなる
・会話をしなくなり、言葉でのコミュニケーションが重要ではなくなる
・食事を摂っても美味しいと思わなくなり食事量が低下する
<看取りケア>
・状態報告及びご家族様の意向を再確認し、面会の提案をする
・利用者様が好んで食べていた食べ物を持って来てもらい食べていただく
・会話よりスキンシップや沈黙にて見守る
~ステージ2~ 死の2週間から1週間前の特徴
・ほぼ眠っており、声をかけると開眼するが徐々に開眼することがなくなってくる
・たまに、混乱して妄想で亡くなったご家族様や誰かと会話をしていることがある
(一説には、死後の世界と交信できるのではないかと言われている)
<看取りケア>
・週1回程度の面会の提案や衣類の提案(本人にとって楽に過ごせる衣装)
・吸痰は無理に行わず、口腔ケアにて痰を除去する。(本人の意識がないと苦しくない)
・本人の意識がありムセこんでいる時は、吸痰を実施する。
・食事は無理に食べてもらわない。
・無理に食べることで身体に負担がかかり、腹水や浮腫、痰の量を増やす原因になる。
<このころに見られる身体の特徴>
血圧の低下や、脈拍が110/分以上になり発熱等による体温の変動、尿量の低下、尿色が濃くなる。発汗が多くなる
~ステージ3~ 死の数日から数時間前の特徴
・呼吸の間隔が長くなる(肩呼吸・下顎呼吸が見られる)
・意識レベルの低下や食事が摂れなくなり、死前喘鳴が聞かれる
(呼吸をすると、喉の奥のほうでゴロゴロと音がする)
・目が半開きになり、その視野はほとんど見えていない
・バイタルサイン(脈拍・心拍数・血圧・体温・血中酸素濃度)の測定ができなくなる。
<看取りケア>
・ご家族様のご意向に合わせて、1日1回の面会の提案
・寝たきりになるため、その人の安楽な姿勢(ポジショニング)を設定する。
・褥瘡(とこずれ)ができないように体の向きを定期的に変える(体位変換)
・こまめに訪室し、状態の観察を行う。
以上が雅秀苑での看取りケアの指標になります。
<ここで豆知識>
・人間には、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚(皮膚感覚)と五感と呼ばれるものがございます。
人の最後まで生きている機能が聴覚と言われています。(死後数分は聞こえているみたいですよ)
ですので、人が亡くなった後でも話しかける事が大事だと言われています。
・死を迎えられた方のお顔が穏やかに幸せそうなお顔をしているのは、人が亡くなる直前に
苦しまないように“エンドルフィン„と言うモルヒネ(鎮痛薬)のような作用をもつホルモンが身体のなかで機能するために人は苦しまなく最後を迎える事ができる。
最後になりますが、私たちが日々接している方はご高齢の方ばかりです。
ご高齢の方に限らず生きていく中でいつ何が起こるかわかりませんし、明日が必ず訪れる保証は難しいと思います。
ですから、利用者様との1日1日を大切にし、毎日の状態観察を行い、いつもと違う感じがあれば、記録や報告することで情報の共有を行っています。
看取りケアを実施していくうえで大切なことだと思っていること、その人らしく最後を迎えるには、その人がどのような最後を迎えたいのか利用者様の思いや家族様のご意向を参考にして看取りケアを実施し、今その人が必要としていることは何だろうと日々考えています。
朝起きてカーテンを開けて朝日を浴びる、毎日の髭剃りや爪切り、大好きだった音楽を聴きながら過ごしていただく等の毎日の日課や、話すことが苦しい、目を中々開いてくれない方でも話しかけてコミュニケーションを実施する「今この人に何ができるのか?」「この人はどうしてほしいのか?」と常に自問自答を繰り返しと、職員一同考えています。
また、ご家族様との関わりも大切にし、定期的に利用者様の状態を報告し、最後を迎えるその時を一緒に過ごせてもらえるように空間の提供など行っています。
出来れば最後の日が訪れないほうが一番いいのですが必ず訪れます。
最後の日が雅秀苑で迎えられてよかったと思えるように頑張ります。
長文になりましたが、最後までお付き合いくださりありがとうございました。

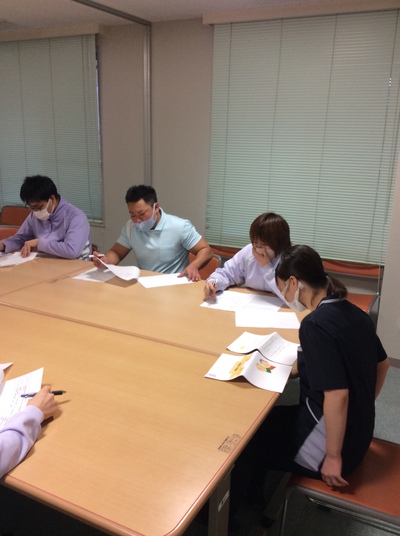
みなさまこんにちは、12月はとても勉強会が多くて毎日ブログ記事の更新作業に追われている ぼくです。
さて今回は、令和2年12月17日に看護師を講師に迎えまして看取りケアについて教えてもらいました。
みなさまも「看取りケア」って何?と思われているでしょうが
看取りケアとは
「近い将来死が避けられないとされた利用者様に対して、身体的苦痛や精神的苦痛を緩和、軽減するとともに人生の最後まで尊厳ある生活を支援する事」
簡単に言いますと「本人らしさを失わず、穏やかに最後の日を迎える」ことです。
看取りケアの中でも、ターミナルケア・ホスピス(緩和ケア)といくつかのケアがありまして
言葉だけならご存じの方もおられると思います。
ターミナルケアとは、終末医療(苦痛緩和・最後を看取る)
ホスピスとは、不治の病(ガン・エイズ等)の終末医療(苦痛緩和・最後を看取る)
また、看取りケアは、在宅や介護施設で行う身体的ケア
ターミナルやホスピスは、病院で行う医療的ケアとしています。
‶食べる„行為について少しお話します。
私たちは「生きるため」体の機能維持のために食事を摂ります。
終末期を迎える高齢者の方は、食欲が減少していきますが、それは体が自然にそうなってくるそうです。
次の段階へ体が以降すると、体内の水分を減らしていき体が楽に最後を迎えられるように
わざと脱水症状になっていきます。
そして、最後を迎える時期が近づくと、眠る時間が長くなり残りの生命をゆっくりと使い切って最後を迎えます。
このように、人の身体も死を迎え入れる準備をしていきます。
ここ雅秀苑では、看取りへと移行するための指標がありそれに準じて看取りの対応を実施しています。
では、雅秀苑の看取り指標を少しご紹介します。
~ステージ1~ 死の3か月から1か月の特徴
・興味がなくなる、眠る時間、まぶたを閉じる時間が長くなる
・会話をしなくなり、言葉でのコミュニケーションが重要ではなくなる
・食事を摂っても美味しいと思わなくなり食事量が低下する
<看取りケア>
・状態報告及びご家族様の意向を再確認し、面会の提案をする
・利用者様が好んで食べていた食べ物を持って来てもらい食べていただく
・会話よりスキンシップや沈黙にて見守る
~ステージ2~ 死の2週間から1週間前の特徴
・ほぼ眠っており、声をかけると開眼するが徐々に開眼することがなくなってくる
・たまに、混乱して妄想で亡くなったご家族様や誰かと会話をしていることがある
(一説には、死後の世界と交信できるのではないかと言われている)
<看取りケア>
・週1回程度の面会の提案や衣類の提案(本人にとって楽に過ごせる衣装)
・吸痰は無理に行わず、口腔ケアにて痰を除去する。(本人の意識がないと苦しくない)
・本人の意識がありムセこんでいる時は、吸痰を実施する。
・食事は無理に食べてもらわない。
・無理に食べることで身体に負担がかかり、腹水や浮腫、痰の量を増やす原因になる。
<このころに見られる身体の特徴>
血圧の低下や、脈拍が110/分以上になり発熱等による体温の変動、尿量の低下、尿色が濃くなる。発汗が多くなる
~ステージ3~ 死の数日から数時間前の特徴
・呼吸の間隔が長くなる(肩呼吸・下顎呼吸が見られる)
・意識レベルの低下や食事が摂れなくなり、死前喘鳴が聞かれる
(呼吸をすると、喉の奥のほうでゴロゴロと音がする)
・目が半開きになり、その視野はほとんど見えていない
・バイタルサイン(脈拍・心拍数・血圧・体温・血中酸素濃度)の測定ができなくなる。
<看取りケア>
・ご家族様のご意向に合わせて、1日1回の面会の提案
・寝たきりになるため、その人の安楽な姿勢(ポジショニング)を設定する。
・褥瘡(とこずれ)ができないように体の向きを定期的に変える(体位変換)
・こまめに訪室し、状態の観察を行う。
以上が雅秀苑での看取りケアの指標になります。
<ここで豆知識>
・人間には、視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚(皮膚感覚)と五感と呼ばれるものがございます。
人の最後まで生きている機能が聴覚と言われています。(死後数分は聞こえているみたいですよ)
ですので、人が亡くなった後でも話しかける事が大事だと言われています。
・死を迎えられた方のお顔が穏やかに幸せそうなお顔をしているのは、人が亡くなる直前に
苦しまないように“エンドルフィン„と言うモルヒネ(鎮痛薬)のような作用をもつホルモンが身体のなかで機能するために人は苦しまなく最後を迎える事ができる。
最後になりますが、私たちが日々接している方はご高齢の方ばかりです。
ご高齢の方に限らず生きていく中でいつ何が起こるかわかりませんし、明日が必ず訪れる保証は難しいと思います。
ですから、利用者様との1日1日を大切にし、毎日の状態観察を行い、いつもと違う感じがあれば、記録や報告することで情報の共有を行っています。
看取りケアを実施していくうえで大切なことだと思っていること、その人らしく最後を迎えるには、その人がどのような最後を迎えたいのか利用者様の思いや家族様のご意向を参考にして看取りケアを実施し、今その人が必要としていることは何だろうと日々考えています。
朝起きてカーテンを開けて朝日を浴びる、毎日の髭剃りや爪切り、大好きだった音楽を聴きながら過ごしていただく等の毎日の日課や、話すことが苦しい、目を中々開いてくれない方でも話しかけてコミュニケーションを実施する「今この人に何ができるのか?」「この人はどうしてほしいのか?」と常に自問自答を繰り返しと、職員一同考えています。
また、ご家族様との関わりも大切にし、定期的に利用者様の状態を報告し、最後を迎えるその時を一緒に過ごせてもらえるように空間の提供など行っています。
出来れば最後の日が訪れないほうが一番いいのですが必ず訪れます。
最後の日が雅秀苑で迎えられてよかったと思えるように頑張ります。
長文になりましたが、最後までお付き合いくださりありがとうございました。
利用者様との接し方 ~利用者様の安心・安全・安楽に向けて~
2021年01月21日
利用者様との接し方 ~利用者様の安心・安全・安楽に向けて~
令和2年12月15日
みなさまこんにちは、寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?
今回は、利用者様との接し方と題しまして接遇の勉強会を行いましたのでご紹介します。
始めに、利用者様との接し方、関わり方はどのようにすれば良いのか質問をしたところ、職員から聞かれた答えは「思いやりを持つ、自分がされて嫌なことをしない、その人の事を知る、尊厳をもつ」と色々な答えが出ました。
では、その答えが実践できているのか職員に質問してみると「忙しい時にできていないこともある、作業になっていることがある、たくさんの方に一度に言われると対応できない」と意見が出ました。
自分が思う利用者様との関わり方ができるように、今まで以上に実践できるにはどうしたらよいのか考えてもらいました。
職員よりでた意見は「専門的な知識を学習する、作業になるのではなく思いやりをもってケアを行っていく、勉強会等を利用してもっと専門的知識を学習する」と日頃の自分を思い起こしながらどうしたらいいのかと考えていました。


今までの自分と、これからの自分と思い描くことができたところで、利用者様の身体的特徴
高齢者ってどう言った特徴があるのかを考えてみました。
特徴として
・運動機能・筋力の低下(廃用症候群になりやすい)
・低栄養になりやすい
・加齢に伴う疾患や慢性疾患を持っている
・認知機能が低下しやすい
・喪失体験をしている
・骨折や内出血をしやすいなど
このようにいろいろな特徴がございますが、体の状態が常に怪我や病気と隣り合わせです。
何かを怠ってしまうとすぐに上記のような状態に陥ってしまいますので、健康管理は特別なものになります。
利用者様の気持ちをより体感してもらうために、実際に利用者様になりきって介助を体験してもらいました。
利用者様役には、左半身麻痺、立位保持困難、重度な拘縮あり、認知症あり、と役になりきってもらい、ベットから車椅子、車椅子からベットへと移乗介助のシーンを想定して、職員に
利用者様が日頃どんな思いをしているか体験してもらいました。


まずは、いつも通りの介助をしてもらい利用者様役には痛かったら素直に痛いと伝える事と
高齢者目線で、これは痛いと思えば素直に「痛い」と伝えることをルールにして体験してもらいました。
利用者様役の職員からは「わきの下に手を入れると痛かった、急に体を動かされると恐い
車椅子で移動するとこんなにスピード感があるんだ」など体験しないとわからない感想が聞かれました。
その聞かれた意見を解決できる介助を次にしてもらうと、体や車椅子を動かす前には「動きますよ、今から車椅子を押しますね、今から車椅子へ移りますから立ち上がってみましょうか?」と声をかけて介助を行っている風景に変化していました。
今までの声掛けでは足りないのではないかと実感している様子でした。
次に、介助者役と利用者様役を交代して介助をしてもらうと、一度利用者様役で経験していることで介助する時に気をつけながら、どうしたら痛くないか、どうしたら恐くないか、麻痺のある人の移乗ってと考えながら介助を行っている姿を目にすることができました。
改めて、利用者様の気持ちを理解することで寄り添う介護、安心で安全で安楽なケアを実践できる勉強会になりました。
引き続き、雅秀苑では、安心、安全、安楽なケアを提供できるように勉強会などを実施して職員のスキルアップに努めてまいります。
最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。
令和2年12月15日
みなさまこんにちは、寒い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?
今回は、利用者様との接し方と題しまして接遇の勉強会を行いましたのでご紹介します。
始めに、利用者様との接し方、関わり方はどのようにすれば良いのか質問をしたところ、職員から聞かれた答えは「思いやりを持つ、自分がされて嫌なことをしない、その人の事を知る、尊厳をもつ」と色々な答えが出ました。
では、その答えが実践できているのか職員に質問してみると「忙しい時にできていないこともある、作業になっていることがある、たくさんの方に一度に言われると対応できない」と意見が出ました。
自分が思う利用者様との関わり方ができるように、今まで以上に実践できるにはどうしたらよいのか考えてもらいました。
職員よりでた意見は「専門的な知識を学習する、作業になるのではなく思いやりをもってケアを行っていく、勉強会等を利用してもっと専門的知識を学習する」と日頃の自分を思い起こしながらどうしたらいいのかと考えていました。
今までの自分と、これからの自分と思い描くことができたところで、利用者様の身体的特徴
高齢者ってどう言った特徴があるのかを考えてみました。
特徴として
・運動機能・筋力の低下(廃用症候群になりやすい)
・低栄養になりやすい
・加齢に伴う疾患や慢性疾患を持っている
・認知機能が低下しやすい
・喪失体験をしている
・骨折や内出血をしやすいなど
このようにいろいろな特徴がございますが、体の状態が常に怪我や病気と隣り合わせです。
何かを怠ってしまうとすぐに上記のような状態に陥ってしまいますので、健康管理は特別なものになります。
利用者様の気持ちをより体感してもらうために、実際に利用者様になりきって介助を体験してもらいました。
利用者様役には、左半身麻痺、立位保持困難、重度な拘縮あり、認知症あり、と役になりきってもらい、ベットから車椅子、車椅子からベットへと移乗介助のシーンを想定して、職員に
利用者様が日頃どんな思いをしているか体験してもらいました。
まずは、いつも通りの介助をしてもらい利用者様役には痛かったら素直に痛いと伝える事と
高齢者目線で、これは痛いと思えば素直に「痛い」と伝えることをルールにして体験してもらいました。
利用者様役の職員からは「わきの下に手を入れると痛かった、急に体を動かされると恐い
車椅子で移動するとこんなにスピード感があるんだ」など体験しないとわからない感想が聞かれました。
その聞かれた意見を解決できる介助を次にしてもらうと、体や車椅子を動かす前には「動きますよ、今から車椅子を押しますね、今から車椅子へ移りますから立ち上がってみましょうか?」と声をかけて介助を行っている風景に変化していました。
今までの声掛けでは足りないのではないかと実感している様子でした。
次に、介助者役と利用者様役を交代して介助をしてもらうと、一度利用者様役で経験していることで介助する時に気をつけながら、どうしたら痛くないか、どうしたら恐くないか、麻痺のある人の移乗ってと考えながら介助を行っている姿を目にすることができました。
改めて、利用者様の気持ちを理解することで寄り添う介護、安心で安全で安楽なケアを実践できる勉強会になりました。
引き続き、雅秀苑では、安心、安全、安楽なケアを提供できるように勉強会などを実施して職員のスキルアップに努めてまいります。
最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。
口腔ケア研修 ~義歯の必要性について~
2021年01月21日
口腔ケア研修 ~義歯の必要性について~
新年 明けまして おめでとうございます。 本年は皆様にとって良い年であるように願っています。
さて、今回は令和2年12月07日(月)に開催されました口腔研修の様子をご紹介します。
雅秀苑では、ハローデンタル様(訪問歯科)が定期的に訪問して利用者様の口腔内の衛生管理をしてくださっています。 その訪問歯科の先生を講師に迎えて、義歯についてと題しまして義歯の必要性と義歯の管理法について教えてもらいました。
義歯と言っても数種類あり、ブリッジ、インプラント、入れ歯(義歯)と種類があります。
なぜそんなに種類があるかと言いますと、基本的に義歯はどんな場所にでも作ることが可能であり、その数種類を使い分けて必要な箇所に制作します。
また、義歯は歯の治療とは違い、口を大きくあけながら治療することがなく、そのもの自体を取り出して修理調整することができると言うメリットがあります。
総入れ歯ともなると、完全に製作するのに約2週間もの期間がかかります。
なぜそこまで時間がかかるのか、もちろん保険制度の問題もありますが、その人の口腔内(お口の中)の情報を正確に知ることが必要になるため、それなりの期間が必要になります。
色々なプロセスを経て義歯は完成を迎えるのですが、義歯を使用し食事をしたとしても昔のように100%の機能回復は難しいそうで、30%~50%程しか回復は見込めないそうです。
理由として、その人の適応力や慣れや調整が必要になるからです。
それでも、物を咬んで飲み込む、食事を楽しむ事が出来たら幸せですよね。
義歯の管理方法ですが、就寝時や未使用時にはコップまたは、義歯ケースの中に水を張り
そこへ義歯を浸けて保管します。
なぜかと言いますと、義歯の歯茎の部分が乾燥により劣化や変形したりします。
また、義歯ケースの中は雑菌の繁殖により、カビなどが発生しやすい環境になるため毎日洗浄して清潔を保つことが必要になります。
ポリグリップ(義歯安定剤)を使用している方がいらっしゃいますが、基本的にポリグリップは使用しないほうがいいらしいです。 ポリグリップがお口の中の衛生環境を悪くするリスクがあり、義歯が合わないまま使用する事で義歯の破損や、顎の骨に過度な負担を与えてしまいます。義歯が合わない時は歯医者さんで調整することが大事です。
また、義歯を使わず放置していると、義歯が合わなくなり再度作り直しが必要になるために
お金や時間がムダになってしまいます。
最後に義歯の必要性についてお話します。 なぜ義歯が必要かと言いますと
食べる楽しみや、物を飲み込みやすくする(嚥下機能の確保)、自歯が全て無くなった時の
見た目の良さ(審美面)
食べる楽しみがなくなってしまうと嫌ですよね?
美味しい物、四季折々の料理、地域の特産、やけ食い、すべての欲望を満たしてくれる義歯ってとても必要になってくると思います。



それでは本年度もここ雅秀苑の勉強会をご紹介できるようにがんばりますのでご声援よろしくお願いします。
新年 明けまして おめでとうございます。 本年は皆様にとって良い年であるように願っています。
さて、今回は令和2年12月07日(月)に開催されました口腔研修の様子をご紹介します。
雅秀苑では、ハローデンタル様(訪問歯科)が定期的に訪問して利用者様の口腔内の衛生管理をしてくださっています。 その訪問歯科の先生を講師に迎えて、義歯についてと題しまして義歯の必要性と義歯の管理法について教えてもらいました。
義歯と言っても数種類あり、ブリッジ、インプラント、入れ歯(義歯)と種類があります。
なぜそんなに種類があるかと言いますと、基本的に義歯はどんな場所にでも作ることが可能であり、その数種類を使い分けて必要な箇所に制作します。
また、義歯は歯の治療とは違い、口を大きくあけながら治療することがなく、そのもの自体を取り出して修理調整することができると言うメリットがあります。
総入れ歯ともなると、完全に製作するのに約2週間もの期間がかかります。
なぜそこまで時間がかかるのか、もちろん保険制度の問題もありますが、その人の口腔内(お口の中)の情報を正確に知ることが必要になるため、それなりの期間が必要になります。
色々なプロセスを経て義歯は完成を迎えるのですが、義歯を使用し食事をしたとしても昔のように100%の機能回復は難しいそうで、30%~50%程しか回復は見込めないそうです。
理由として、その人の適応力や慣れや調整が必要になるからです。
それでも、物を咬んで飲み込む、食事を楽しむ事が出来たら幸せですよね。
義歯の管理方法ですが、就寝時や未使用時にはコップまたは、義歯ケースの中に水を張り
そこへ義歯を浸けて保管します。
なぜかと言いますと、義歯の歯茎の部分が乾燥により劣化や変形したりします。
また、義歯ケースの中は雑菌の繁殖により、カビなどが発生しやすい環境になるため毎日洗浄して清潔を保つことが必要になります。
ポリグリップ(義歯安定剤)を使用している方がいらっしゃいますが、基本的にポリグリップは使用しないほうがいいらしいです。 ポリグリップがお口の中の衛生環境を悪くするリスクがあり、義歯が合わないまま使用する事で義歯の破損や、顎の骨に過度な負担を与えてしまいます。義歯が合わない時は歯医者さんで調整することが大事です。
また、義歯を使わず放置していると、義歯が合わなくなり再度作り直しが必要になるために
お金や時間がムダになってしまいます。
最後に義歯の必要性についてお話します。 なぜ義歯が必要かと言いますと
食べる楽しみや、物を飲み込みやすくする(嚥下機能の確保)、自歯が全て無くなった時の
見た目の良さ(審美面)
食べる楽しみがなくなってしまうと嫌ですよね?
美味しい物、四季折々の料理、地域の特産、やけ食い、すべての欲望を満たしてくれる義歯ってとても必要になってくると思います。
それでは本年度もここ雅秀苑の勉強会をご紹介できるようにがんばりますのでご声援よろしくお願いします。
認知症の勉強会
2021年01月06日
認知症の勉強会
令和2年11月24日(火)
みなさまこんにちは、いつも雅秀苑のブログを見てくださり、ありがとうございます。
さて今回は、昨日行われました認知症の勉強会をご紹介します。
認知症の勉強会では、ユマニチュードの勉強会を重点的に行っています。
みなさん、ユマニチュードってご存じでしょうか?
ユマニチュードとは、知的、感情、言語による包括的コミュニケーション技法の事です。
ユマニチュードでは、4つの柱を軸にコミュニケーションを組み立てていく技術で
4つの柱とは、見る・触れる・話す・立つと、4つの技術で成り立っています。
以前にもユマニチュードの勉強会を開催していますので、7月度の記事を見ていただけたら
幸いです。
さて、今回の認知症の勉強会は、ユマニチュードの実践的活用としまして、実際に利用者様役と介助者役に分かれてユマニチュードを実践してもらいました。



この実技にはルールがありまして、ユマニチュードを実践しながら車椅子の移動介助をする事と、利用者様役に同意が得られなければ動かしてはいけない事の2つのルールを決めました。
介助者役のスタッフは、ユマニチュードの4つ柱を活用して利用者様とコミュニケーションをとりつつ車椅子の移動介助を行っていました。
それとは対照的で、なかなか同意をもらえない職員が悪戦苦闘していました。
実践を通じて、コミュニケーションの重要性が理解できました。
続きまして、「長谷川式簡易知能スケール」の体験を行いました。
みなさま、長谷川式簡易知能スケールってご存じでしょうか?
1974年に聖マリアンナ医科大学神経精神科教授だった長谷川和夫氏らによって公表された認知症の診断指標です。
見当識、計算力、注意力、記銘力、再生と5つの機能が正常に機能しているかを簡単な質問や計算などを用いて点数をつけていきます。
30点満点中、20点以下は認知機能の疑いありと判断されます。
質問内容は「今日は何月何日ですか?」「出身地はどこですか?」「100から順に7を引いた数を行ってみてください」など、簡単な質問になっています。
この長谷川式簡易知能スケールを作るにあたり、高齢者の集中力を考慮して短時間で回答できるもの 視力の衰えを考慮して、視覚的要素を問題にしないと色々と配慮がなされた指標になっています。 この長谷川式簡易知能スケールを実際にスタッフに受けてもらいました。



写真だけを見ているとまるで、尋問を受けているような感じに見えますが、ちゃんと質問者と回答者にわかれて行っています。
さて、結果はと言いますと、もちろんみなさん20点以上ありました。
次に体験したのは、警視庁より全国の運転試験場にて使用されている、高齢者運転免許返納の際に用いられる認知機能検査と言う簡単なテストを体験してもらいました。
車の運転免許に関する事だけに少しだけ複雑な質問でした。
視覚に関する質問(絵を見て答える)記憶に関する質問(単語を覚える)等
長谷川式簡易知能スケールよりは少しだけ複雑です。
複雑なだけにみなさん真剣に回答していました。


以上で今回の認知症の勉強会のご紹介を終わりにします。
次回も勉強会の様子をご紹介しますので、またのぞきにきてください。
令和2年11月24日(火)
みなさまこんにちは、いつも雅秀苑のブログを見てくださり、ありがとうございます。
さて今回は、昨日行われました認知症の勉強会をご紹介します。
認知症の勉強会では、ユマニチュードの勉強会を重点的に行っています。
みなさん、ユマニチュードってご存じでしょうか?
ユマニチュードとは、知的、感情、言語による包括的コミュニケーション技法の事です。
ユマニチュードでは、4つの柱を軸にコミュニケーションを組み立てていく技術で
4つの柱とは、見る・触れる・話す・立つと、4つの技術で成り立っています。
以前にもユマニチュードの勉強会を開催していますので、7月度の記事を見ていただけたら
幸いです。
さて、今回の認知症の勉強会は、ユマニチュードの実践的活用としまして、実際に利用者様役と介助者役に分かれてユマニチュードを実践してもらいました。
この実技にはルールがありまして、ユマニチュードを実践しながら車椅子の移動介助をする事と、利用者様役に同意が得られなければ動かしてはいけない事の2つのルールを決めました。
介助者役のスタッフは、ユマニチュードの4つ柱を活用して利用者様とコミュニケーションをとりつつ車椅子の移動介助を行っていました。
それとは対照的で、なかなか同意をもらえない職員が悪戦苦闘していました。
実践を通じて、コミュニケーションの重要性が理解できました。
続きまして、「長谷川式簡易知能スケール」の体験を行いました。
みなさま、長谷川式簡易知能スケールってご存じでしょうか?
1974年に聖マリアンナ医科大学神経精神科教授だった長谷川和夫氏らによって公表された認知症の診断指標です。
見当識、計算力、注意力、記銘力、再生と5つの機能が正常に機能しているかを簡単な質問や計算などを用いて点数をつけていきます。
30点満点中、20点以下は認知機能の疑いありと判断されます。
質問内容は「今日は何月何日ですか?」「出身地はどこですか?」「100から順に7を引いた数を行ってみてください」など、簡単な質問になっています。
この長谷川式簡易知能スケールを作るにあたり、高齢者の集中力を考慮して短時間で回答できるもの 視力の衰えを考慮して、視覚的要素を問題にしないと色々と配慮がなされた指標になっています。 この長谷川式簡易知能スケールを実際にスタッフに受けてもらいました。
写真だけを見ているとまるで、尋問を受けているような感じに見えますが、ちゃんと質問者と回答者にわかれて行っています。
さて、結果はと言いますと、もちろんみなさん20点以上ありました。
次に体験したのは、警視庁より全国の運転試験場にて使用されている、高齢者運転免許返納の際に用いられる認知機能検査と言う簡単なテストを体験してもらいました。
車の運転免許に関する事だけに少しだけ複雑な質問でした。
視覚に関する質問(絵を見て答える)記憶に関する質問(単語を覚える)等
長谷川式簡易知能スケールよりは少しだけ複雑です。
複雑なだけにみなさん真剣に回答していました。
以上で今回の認知症の勉強会のご紹介を終わりにします。
次回も勉強会の様子をご紹介しますので、またのぞきにきてください。
♪12月のデイケア♪
2020年12月30日
12月のデイケア
松花堂弁当

<メニュー>
ごはん
サイコロステーキ
ほうれん草のソテー
ポテトサラダ
ポタージュスープ
フルーツ(オレンジ)
やっぱりお肉が好き♡
サイコロステーキは喜んでいただけました(*^-^*)
お寿司

<メニュー>
マグロ、海老、サーモン、たまご
巻き寿司、赤だし、みかん
~おかわり~
漬けマグロ、炙りサーモン
海老、たまご、巻き寿司
ツナマヨ巻き、穴子きゅうり
おかわり分は、デイケアの冷蔵庫内に保管し温度管理もしっかりとさせていただきました。安心、安全、美味しく、楽しいお寿司の会が催されました(^^♪



このようなご時世ですので、バイキングではなく、おかわりは、聞き取り制にして、職員がお皿に盛り付ける方式にしてみましたが、皆さんおかわりをたくさんしていただき、美味しそうに召し上がられていました。11月、12月、1月の3回実施予定です。楽しんでいただければと思います。
クリスマス会
メリークリスマス
12/21、12/22の二日間はデイケアのクリスマス会でした。皆さん、サンタの帽子をかぶられて、職員はトナカイに扮して楽しまれていました。

クリスマス餃子パーティー✨


餃子と一緒にノンアルコールの飲み物を提供しました
メインはやっぱりクリスマスケーキホールケーキをデイケアの職員が、綺麗にトッピングして完成!!
イチゴが乗っていて美味しそうですね。

そしてクリスマスが終わると、今年ももう終わりですね。今年も一年ありがとうございました。よいお年をお迎えください☆
松花堂弁当

<メニュー>
ごはん
サイコロステーキ
ほうれん草のソテー
ポテトサラダ
ポタージュスープ
フルーツ(オレンジ)
やっぱりお肉が好き♡
サイコロステーキは喜んでいただけました(*^-^*)
お寿司

<メニュー>
マグロ、海老、サーモン、たまご
巻き寿司、赤だし、みかん
~おかわり~
漬けマグロ、炙りサーモン
海老、たまご、巻き寿司
ツナマヨ巻き、穴子きゅうり
おかわり分は、デイケアの冷蔵庫内に保管し温度管理もしっかりとさせていただきました。安心、安全、美味しく、楽しいお寿司の会が催されました(^^♪



このようなご時世ですので、バイキングではなく、おかわりは、聞き取り制にして、職員がお皿に盛り付ける方式にしてみましたが、皆さんおかわりをたくさんしていただき、美味しそうに召し上がられていました。11月、12月、1月の3回実施予定です。楽しんでいただければと思います。
クリスマス会
メリークリスマス
12/21、12/22の二日間はデイケアのクリスマス会でした。皆さん、サンタの帽子をかぶられて、職員はトナカイに扮して楽しまれていました。

クリスマス餃子パーティー✨


餃子と一緒にノンアルコールの飲み物を提供しました
メインはやっぱりクリスマスケーキホールケーキをデイケアの職員が、綺麗にトッピングして完成!!
イチゴが乗っていて美味しそうですね。

そしてクリスマスが終わると、今年ももう終わりですね。今年も一年ありがとうございました。よいお年をお迎えください☆
♪12月の行事食♪
2020年12月30日
12月の行事食
メリークリスマス
今年の12/24は朝から雨が降っていましたね。
雨は夜更け過ぎに~ 雪へと…
雪へと変わらずに、雨も止んで、すっかりと夜からは天気は回復しました
雅秀苑では、今年は12/23にクリスマス会を各フロアで実施されています。
今年も厨房の調理師に元パティシエの方がいるので、パティシエ監修のもと
クリスマスノエルを手作りで焼いてくれました✨

しっとりと出来上がっており、すごく美味しかったです。
食べづらい方用のおやつは二層のムースでイチゴソースを挟んだ一品です☆

12/25クリスマス当日の昼食はクリスマスメニューで提供しました。

『海老ピラフ、クリスマスプレート(手作りハンバーグ、ナポリタン)、ポタージュスープ、フルーツ(オレンジ)』
おやつはイチゴマフィンを可愛くトッピングをして提供しました。

皆様より、「美味しい」という声をいただき、喜んでいただけたと思います。
また、12/21は冬至でした

・冬至とは北半球で太陽の位置が1年で最も低くなり、太陽の出ている時間が最も
短くなる日の事です。
冬至は太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力がよみがえっていくとされ、冬至を境に運が向いてくると信じられていました。
・冬至の日に柚子湯に入るのは柚子=「融通」がきく、冬至=「湯治」といった語呂合わせからと思われていますが、もともとは運を呼び込む前に厄払いをするための禊が由来と言われています。冬が旬の柚子は香りも強く、強い香りのもとには邪気が起こらないという考えもありました。また、柚子は実るまで長い年月がかかるので、長年の苦労が実りますようにとの願いも込められています。
<柚子の栄養成分と効能について>
・ヘスペリジン:血管を強化して血流を改善する働きがあり冷え性や高血圧を予防する効果があると考えられています。
・ビタミンC:白血球の免疫力を高め、風邪やウイルスに対する抵抗性を強めます。
・リモネン:香り成分の1種で不安やストレスを緩和、リラックス効果があります。
メリークリスマス
今年の12/24は朝から雨が降っていましたね。
雨は夜更け過ぎに~ 雪へと…
雪へと変わらずに、雨も止んで、すっかりと夜からは天気は回復しました
雅秀苑では、今年は12/23にクリスマス会を各フロアで実施されています。
今年も厨房の調理師に元パティシエの方がいるので、パティシエ監修のもと
クリスマスノエルを手作りで焼いてくれました✨

しっとりと出来上がっており、すごく美味しかったです。
食べづらい方用のおやつは二層のムースでイチゴソースを挟んだ一品です☆

12/25クリスマス当日の昼食はクリスマスメニューで提供しました。

『海老ピラフ、クリスマスプレート(手作りハンバーグ、ナポリタン)、ポタージュスープ、フルーツ(オレンジ)』
おやつはイチゴマフィンを可愛くトッピングをして提供しました。

皆様より、「美味しい」という声をいただき、喜んでいただけたと思います。
また、12/21は冬至でした

・冬至とは北半球で太陽の位置が1年で最も低くなり、太陽の出ている時間が最も
短くなる日の事です。
冬至は太陽の力が一番弱まった日であり、この日を境に再び力がよみがえっていくとされ、冬至を境に運が向いてくると信じられていました。
・冬至の日に柚子湯に入るのは柚子=「融通」がきく、冬至=「湯治」といった語呂合わせからと思われていますが、もともとは運を呼び込む前に厄払いをするための禊が由来と言われています。冬が旬の柚子は香りも強く、強い香りのもとには邪気が起こらないという考えもありました。また、柚子は実るまで長い年月がかかるので、長年の苦労が実りますようにとの願いも込められています。
<柚子の栄養成分と効能について>
・ヘスペリジン:血管を強化して血流を改善する働きがあり冷え性や高血圧を予防する効果があると考えられています。
・ビタミンC:白血球の免疫力を高め、風邪やウイルスに対する抵抗性を強めます。
・リモネン:香り成分の1種で不安やストレスを緩和、リラックス効果があります。
☆雅秀苑 秋祭り☆
2020年12月05日
秋も深まり冬の足音も聞かれるようになりましたが、皆様。いかがお過ごしでしょうか?


毎年恒例の帝塚山福祉会 南港祭りがコロナ禍の影響で中止となりました。楽しみにしていた催しだけに残念です。

しかし、このまま何もしなくて終わるのは「嫌だ!」と言う声も上がり、規模を縮小するとともに安全に楽しんで頂けるように、スタッフ間で感染対策を話し合い、各フロアーで秋祭りの開催に向け、趣向を凝らした準備が行われました。その模様をお伝えします。
準備は開催日前より行い屋台や飾りつけの提灯など、利用者様とスタッフが共同で作成しました。ある利用者からは「祭りするんやろ!楽しみにしてるで」と言われる方もいらっしゃいました。当日は全国の有名なお祭りの映像をプロジェクターで投影し、気分を盛り上げてもらう所から始まりました。お手製の屋台を作り、くじ引きで景品を当たり、たこ焼きやフランクフルトを提供します。たこ焼きの生地は柔らかくなるように手作り、ソースにはトロミを付け、フランクフルトは切込みが入り食べやすい様に工夫されていました。

屋台の回り方も一方通行にして食席も予め決めた事で、混雑が避けられていました。
久しぶりに飲むラムネは「懐かしいなぁ。中のビー玉は取れないの」「炭酸を飲むのは久しぶりや」など様々な声が聞かれました。
くじ引きはハズレなしで、利用者様全員に引いて頂き、1等が当たった方は大喜びしていました。もちろん、くじ引きの景品は全員にもれなくあります。
秋祭り中は、あちらこちらで笑い声が聞かれ、利用者様と楽しい時間を過ごす事ができました。

次回はクリスマス会を予定しています
今後も利用者様が楽しんで頂ける催しを考えて参ります。



毎年恒例の帝塚山福祉会 南港祭りがコロナ禍の影響で中止となりました。楽しみにしていた催しだけに残念です。


しかし、このまま何もしなくて終わるのは「嫌だ!」と言う声も上がり、規模を縮小するとともに安全に楽しんで頂けるように、スタッフ間で感染対策を話し合い、各フロアーで秋祭りの開催に向け、趣向を凝らした準備が行われました。その模様をお伝えします。

準備は開催日前より行い屋台や飾りつけの提灯など、利用者様とスタッフが共同で作成しました。ある利用者からは「祭りするんやろ!楽しみにしてるで」と言われる方もいらっしゃいました。当日は全国の有名なお祭りの映像をプロジェクターで投影し、気分を盛り上げてもらう所から始まりました。お手製の屋台を作り、くじ引きで景品を当たり、たこ焼きやフランクフルトを提供します。たこ焼きの生地は柔らかくなるように手作り、ソースにはトロミを付け、フランクフルトは切込みが入り食べやすい様に工夫されていました。

屋台の回り方も一方通行にして食席も予め決めた事で、混雑が避けられていました。
久しぶりに飲むラムネは「懐かしいなぁ。中のビー玉は取れないの」「炭酸を飲むのは久しぶりや」など様々な声が聞かれました。
くじ引きはハズレなしで、利用者様全員に引いて頂き、1等が当たった方は大喜びしていました。もちろん、くじ引きの景品は全員にもれなくあります。

秋祭り中は、あちらこちらで笑い声が聞かれ、利用者様と楽しい時間を過ごす事ができました。


次回はクリスマス会を予定しています

今後も利用者様が楽しんで頂ける催しを考えて参ります。

感染症防止の勉強会
2020年11月02日
感染症防止の勉強会
令和2年9月15日
皆さんこんにちは、いつも雅秀苑のブログを見ていただきありがとうございます。
さて、今回ご紹介する勉強会は感染症防止と題して看護師に講師をしていただきました。
感染症といいましても色々とあります。
・新型コロナウィルス
・インフルエンザウィルス
・ノロウィルス
・MRSA
・HIVウィルス
・梅毒
・風邪…など
我々はご高齢の利用者様に接することが仕事です。
ご高齢の利用者様が新型コロナウィルスに感染すると死に直面する危険性があります。
ここ雅秀苑では、いまだ新型コロナウィルスに利用者様、職員も感染者はいません。
日頃より感染症にかからないように気をつけ、感染症の知識をつけるための教育等を行っています。
今日は、感染症の勉強会の一つでガウンテクニックの講習会を行いましたので少しご紹介します。




これは、ビニール製のガウンで衣類にウィルスが付かないようにするための防護服です。
その他にも、ビニール製の手袋、マスク、フェイスガード、このようなものを装着して
自分の体にウィルスが付かないように防ぐものです。
ウィルスは目には見えないもので、自分の体に付着したままほかの人へ接触してしまうとその人がウィルスに感染する恐れがあるので、感染予防のために着用します。
ガウンテクニックとは、ビニールガウンに付着しているウィルスを自分の体に付着しないよう脱ぐためのテクニックです。
今回は、ガウンに付着したウィルスを自分の体に付着しないように脱ぐ、ガウンテクニックの指導をしてもらいました。
その他に、手袋の外し方、マスクの外し方、手洗いの方法と感染予防に最大限の工夫を行っています。
職員にも、入職してから感染症の対応を経験したことがない人や、以前に別の感染症対策で使用したことがある人と様々で、悪戦苦闘です。
ガウンを外すこと一つをとってみても、技術が必要になってきます。
新型コロナウィルスに感染しない事にこしたことはないですが、しっかりと対応を準備することで
混乱を防ぐことができると実感しました。
引き続き、感染症対策に力をいれて頑張っていきますので、皆様におかれましても
コロナに負けないようにがんばってください。
令和2年9月15日
皆さんこんにちは、いつも雅秀苑のブログを見ていただきありがとうございます。
さて、今回ご紹介する勉強会は感染症防止と題して看護師に講師をしていただきました。
感染症といいましても色々とあります。
・新型コロナウィルス
・インフルエンザウィルス
・ノロウィルス
・MRSA
・HIVウィルス
・梅毒
・風邪…など
我々はご高齢の利用者様に接することが仕事です。
ご高齢の利用者様が新型コロナウィルスに感染すると死に直面する危険性があります。
ここ雅秀苑では、いまだ新型コロナウィルスに利用者様、職員も感染者はいません。
日頃より感染症にかからないように気をつけ、感染症の知識をつけるための教育等を行っています。
今日は、感染症の勉強会の一つでガウンテクニックの講習会を行いましたので少しご紹介します。
これは、ビニール製のガウンで衣類にウィルスが付かないようにするための防護服です。
その他にも、ビニール製の手袋、マスク、フェイスガード、このようなものを装着して
自分の体にウィルスが付かないように防ぐものです。
ウィルスは目には見えないもので、自分の体に付着したままほかの人へ接触してしまうとその人がウィルスに感染する恐れがあるので、感染予防のために着用します。
ガウンテクニックとは、ビニールガウンに付着しているウィルスを自分の体に付着しないよう脱ぐためのテクニックです。
今回は、ガウンに付着したウィルスを自分の体に付着しないように脱ぐ、ガウンテクニックの指導をしてもらいました。
その他に、手袋の外し方、マスクの外し方、手洗いの方法と感染予防に最大限の工夫を行っています。
職員にも、入職してから感染症の対応を経験したことがない人や、以前に別の感染症対策で使用したことがある人と様々で、悪戦苦闘です。
ガウンを外すこと一つをとってみても、技術が必要になってきます。
新型コロナウィルスに感染しない事にこしたことはないですが、しっかりと対応を準備することで
混乱を防ぐことができると実感しました。
引き続き、感染症対策に力をいれて頑張っていきますので、皆様におかれましても
コロナに負けないようにがんばってください。
敬老会
2020年10月30日
 敬老会
敬老会
毎年恒例となっている行事、敬老会の様子をお伝えします。

各フロアーで趣向を凝らし、独自色を出した催しが行われました。
美空ひばりの演歌道を大型スクリーンで上映したフロアーでは、曲に合わせ楽しそうに口ずさむ利用者様がおられました。また、スタッフが炭坑節を踊ったフロアーでは、車椅子利用の利用者様が、手拍子をされて鑑賞されていました。
長寿の表彰状を受け取る際に、レッドカーペットのような敷物を敷き、その上を歩く演出をしたフロアーでは、ご利用者様が「ここを通るの?」「何が出てくるの?」など興味津々で、活気あふれる声が聴かれました。
最後は職員が選りすぐった、長寿のお祝いの記念品を贈呈しました。皆さん、喜んでくださり、うれしかったです。

9/16(水)には敬老膳として、常食の方には『お赤飯、彩りあられ揚げ、炊き合わせ、
南瓜まんじゅう、茶碗蒸し、フルーツ』を提供しました。海老のあられ揚げはカラフルで可愛いあられがついていて、利用者様も「美味しいわ。見た目もきれいだし。毎日でも食べたいわ。」と大変喜んでくださりました。


嚥下食の方には、ソフト食で『あずき粥、エビフライムース、炊き合わせ、南瓜の煮物、
フルーツ、茶わん蒸し』を提供しました。炊き合わせの綺麗にかたどられた竹の子などを見て、「きれいね。食べるのがもったいない。」と笑顔でお話してくださいました。


敬老会当日には、常食の方には『紅白のお饅頭』を、嚥下食の方には『水ようかん』を提供しました。お祝い事には欠かせない「紅白饅頭」。皆様「懐かしいわ。今日は記念品も頂いて、美味しい物も食べて幸せです。」と喜んでくださりました。


新型コロナウイルスで面会制限も継続されている中、少しでもご利用者様に喜んで頂ける催しを今後も企画して参ります。

事故対策委員による、事故報告書の書き方について
2020年10月27日
事故対策委員による、事故報告書の書き方について
令和2年9月9日
皆さんこんにちは、すっかり朝晩涼しくなり過ごしやすい気候になりましたが、どうお過ごしでしょうか?
さて、今回ご紹介する勉強会は事故対策委員による事故報告書の書き方についてです。
当施設におきましては、利用者様が転倒や転落、表皮剥離その他処置を必要とするものが起こると事故報告書を作成し、同じことが起こらないように再発防止の分析資料として使用しています。
また、これは危険ではないのか、利用者様の動作の中にヒヤッとした事や、ハッとしたことがあればヒヤリハット報告として、作成しています。
もちろん、利用者様に事故がないことが一番ですが、細心の注意を払っていても事故はおきてしまいます。
事故が起きた場合、常に細心の注意を払って日々のケアを実施していても、要因があるものです。
その要因を浮き彫りにし、再発防止策を考え同じ事故が起きないように情報の共有に記録として残しています。
その記録の書き方をどのように行ったらいいのかを考えてみました。


記録の書き方としまして、5W1H(誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どうしたのか)を客観的に、事実だけをありのままに記録します。
例を挙げると、利用者様が「右側臥位に床で横たわっていた」、「右側臥位で転倒しているところを発見」と記すのではなく『右側臥位で床に横たわっているところを発見』となります。
転倒したところを目撃したわけではないので、この段階では転倒したのか否か断定できないからです。
以上を踏まえて、架空の事例をもとに事故報告書を皆さんに記録してもらいました。

この情報をもとに事故の要因を考えて、今後の再発防止策を考えてみます。


各々考えた要因と、その再発防止策を発表し意見を共有、その後ディスカッションしてみました。


事故の要因は限定されますが、再発防止策は人それぞれで、色々な観点からの考え方が聞けました。
中には思いもよらなかった素晴らしい再発防止策が聞けて、勉強になりました。
事故が起きないことが望みですが、事故はおきてしまいます。
ただ、二度と同じ事故が起きないように事故報告書をもとに、再発防止策を考えて、利用者様に過ごしやすい環境を提供することが私たちの使命だと思っています。
ここまでお付き合いいただきありがとうございます。
次回もまたご覧いただけたらうれしいです。
令和2年9月9日
皆さんこんにちは、すっかり朝晩涼しくなり過ごしやすい気候になりましたが、どうお過ごしでしょうか?
さて、今回ご紹介する勉強会は事故対策委員による事故報告書の書き方についてです。
当施設におきましては、利用者様が転倒や転落、表皮剥離その他処置を必要とするものが起こると事故報告書を作成し、同じことが起こらないように再発防止の分析資料として使用しています。
また、これは危険ではないのか、利用者様の動作の中にヒヤッとした事や、ハッとしたことがあればヒヤリハット報告として、作成しています。
もちろん、利用者様に事故がないことが一番ですが、細心の注意を払っていても事故はおきてしまいます。
事故が起きた場合、常に細心の注意を払って日々のケアを実施していても、要因があるものです。
その要因を浮き彫りにし、再発防止策を考え同じ事故が起きないように情報の共有に記録として残しています。
その記録の書き方をどのように行ったらいいのかを考えてみました。
記録の書き方としまして、5W1H(誰が、いつ、どこで、何を、なぜ、どうしたのか)を客観的に、事実だけをありのままに記録します。
例を挙げると、利用者様が「右側臥位に床で横たわっていた」、「右側臥位で転倒しているところを発見」と記すのではなく『右側臥位で床に横たわっているところを発見』となります。
転倒したところを目撃したわけではないので、この段階では転倒したのか否か断定できないからです。
以上を踏まえて、架空の事例をもとに事故報告書を皆さんに記録してもらいました。
この情報をもとに事故の要因を考えて、今後の再発防止策を考えてみます。
各々考えた要因と、その再発防止策を発表し意見を共有、その後ディスカッションしてみました。
事故の要因は限定されますが、再発防止策は人それぞれで、色々な観点からの考え方が聞けました。
中には思いもよらなかった素晴らしい再発防止策が聞けて、勉強になりました。
事故が起きないことが望みですが、事故はおきてしまいます。
ただ、二度と同じ事故が起きないように事故報告書をもとに、再発防止策を考えて、利用者様に過ごしやすい環境を提供することが私たちの使命だと思っています。
ここまでお付き合いいただきありがとうございます。
次回もまたご覧いただけたらうれしいです。
アサーティブコミュニケーション講習会
2020年10月27日
アサーティブコミュニケーション講習会
令和2年9月24日(水)
みなさまこんにちは、雅秀苑のブログを見ていただきありがとうございます。
今日は、先日行われました勉強会をご紹介したいと思います。


今回行われました勉強会は、アサーティブコミュニケーションです。
アサーティブって聞きなれない言葉と思いますので、少しご紹介します。
アサーティブとは「自分の気持ちや考えを、まっすぐに表現するやり方の事をアサーティブな態度といいます。 これは、コミュニケーション技術の一つです。
「言いたいことを相手に伝えることができたら、どれだけ気分がすっきりするか」
「相手も尊重する伝え方をすればするほど、どれだけお互いが気持ちいいか」
こういった、自分の気持ちを抑えずに伝え、尚且つ自分自身も大切にするコミュニケーションを【アサーション】といいます。
アサーションとは「自他尊重の自己表現」自分も相手も大切にする自己表現です。
では、例題を使ってアサーションをしてみましょう。
(例)
ファミリーレストランで、お肉を頼んだのにお魚がきました。
どのような反応、対応しますか?
自分も相手も大切にする自己表現(アサーション)を使用するとこうなります。
・自分はお肉を頼んだのに、間違えてお魚がきています。
自分はお肉が食べたいので、交換してもらえませんか?
それが難しいのであれば、このお魚をたべます。
この様な対応をすることで、アサーションを目指したコミュニケーションはより深いものになり、相手とも豊かな関係性を実現できることでしょう。
アサーションを理解いただけたところで、ご自身のコミュニケーションタイプの診断をしてみましょう。
A
・人前で弱さをさらけ出すのが苦手である (〇・×)
・人の悪いところを指摘することがよくある (〇・×)
・自分の思い通りならないとイライラしてしまう(〇・×)
・他人のミスについつい厳しくなってしまう (〇・×)
〇の数 個 ×の数 個
B
・引っ込み思案なところがある (〇・×)
・自分に自信がない (〇・×)
・相手の意見に合わせて行動することがある(〇・×)
・相手に認められたいと期待することがある(〇・×)
・相手に反論されると言い返せなくなる (〇・×)
〇の数 個 ×の数 個
C
・他人に正直な気持ちを打ち明けることができる (〇・×)
・常に積極的に行動することができる (〇・×)
・人が多い場でも自己主張ができる (〇・×)
・苦手な人との会話も柔軟にこなせる (〇・×)
・相手に非難されても自分を卑下せず、さらに相手の意見も尊重できる(〇・×)
〇の数 個 ×の数 個
A、B、Cと各項目がありますが、〇の数が一番多い項目はどの項目ですか?
各項目の〇の数がほかの項目に比べて多い項目で、コミュニケーションタイプが別れます。
Aの項目で〇の数が多かった方
・攻撃的自己表現タイプ(アグレッシブタイプ)
表現の仕方として、自分の欲求を通す、相手に命令する、大声で怒鳴る、相手を操作する、一見すると自分の言いたいことは言えているように思いますが、攻撃的表現をされた側は傷つき、萎縮し、攻撃的人物から離れていく事になります。
その結果、主張を通したものの、後味の悪い気分になり最終的には孤立することになります。
Bの項目で〇の数が多かった方
・非主張的自己表現タイプ(ノンアサーティブタイプ)
自分の考えや主張を表現することなく相手に合わせる、自分に自信がなく本意でなくて
も相手の主張を受け入れるので、ストレスを感じやすい。
このタイプは、言いたいことがあるのに自分の意見や気持ちを言わず、言い出せない人が多く言ったところで相手に伝わりにくい傾向があります。
非自己表現的表現を続けていると、相手から「なんでも言うことを聞いてくれる都合のいい人」と思われてしまいます。
それが加速すると、本来はしたくない役割を任されたり都合よく利用されたりします。
Cの項目で〇の数が多かった方
・アサーティブ自己表現タイプ(アサーティブタイプ)
相手の気持ちや受け止め方に配慮しながら自分の考えや主張を相手に伝える
相手と意見が対立した時でも誠実に対話することでお互いの妥協点を探り問題解決を目指す。相手が苦手なタイプでも論理的に話をすることができる
ご自身のコミュニケーションタイプはわかりましたか?
もう少しわかりやすく例えるなら、国民的アニメ、ドラえもんのキャラクターで例える
ことができますのでご紹介します。
アグレッシブタイプ→ジャイアン
ノンアサーティブタイプ→のび太君
アサーティブタイプ→しずかちゃん
各キャラクターがどんな人物かはみなさまご存じかと思いますので省かせてもらいます。
最後は2人1組になり、言葉だけで説明された絵をどれだけ正確に書けるか伝言ゲーム
を行いました。


最後は2人1組になり、言葉だけで説明された絵をどれだけ正確に書けるか伝言ゲーム
を行いました。


絵の線がはっきりしているほうが答えですが、いかに言葉をうまく伝えるか、情報を聞
き出すか、情報を送る、受け取るためのコミュニケーション能力が重要だと実感しまし
た。
ここまでお付き合いくださりありがとうございます。
こんな感じで勉強会も理解しやすさを求めて飽きないように考えながら実施しています。
みなさまにも楽しさが伝わればうれしいです。
令和2年9月24日(水)
みなさまこんにちは、雅秀苑のブログを見ていただきありがとうございます。
今日は、先日行われました勉強会をご紹介したいと思います。
今回行われました勉強会は、アサーティブコミュニケーションです。
アサーティブって聞きなれない言葉と思いますので、少しご紹介します。
アサーティブとは「自分の気持ちや考えを、まっすぐに表現するやり方の事をアサーティブな態度といいます。 これは、コミュニケーション技術の一つです。
「言いたいことを相手に伝えることができたら、どれだけ気分がすっきりするか」
「相手も尊重する伝え方をすればするほど、どれだけお互いが気持ちいいか」
こういった、自分の気持ちを抑えずに伝え、尚且つ自分自身も大切にするコミュニケーションを【アサーション】といいます。
アサーションとは「自他尊重の自己表現」自分も相手も大切にする自己表現です。
では、例題を使ってアサーションをしてみましょう。
(例)
ファミリーレストランで、お肉を頼んだのにお魚がきました。
どのような反応、対応しますか?
自分も相手も大切にする自己表現(アサーション)を使用するとこうなります。
・自分はお肉を頼んだのに、間違えてお魚がきています。
自分はお肉が食べたいので、交換してもらえませんか?
それが難しいのであれば、このお魚をたべます。
この様な対応をすることで、アサーションを目指したコミュニケーションはより深いものになり、相手とも豊かな関係性を実現できることでしょう。
アサーションを理解いただけたところで、ご自身のコミュニケーションタイプの診断をしてみましょう。
A
・人前で弱さをさらけ出すのが苦手である (〇・×)
・人の悪いところを指摘することがよくある (〇・×)
・自分の思い通りならないとイライラしてしまう(〇・×)
・他人のミスについつい厳しくなってしまう (〇・×)
〇の数 個 ×の数 個
B
・引っ込み思案なところがある (〇・×)
・自分に自信がない (〇・×)
・相手の意見に合わせて行動することがある(〇・×)
・相手に認められたいと期待することがある(〇・×)
・相手に反論されると言い返せなくなる (〇・×)
〇の数 個 ×の数 個
C
・他人に正直な気持ちを打ち明けることができる (〇・×)
・常に積極的に行動することができる (〇・×)
・人が多い場でも自己主張ができる (〇・×)
・苦手な人との会話も柔軟にこなせる (〇・×)
・相手に非難されても自分を卑下せず、さらに相手の意見も尊重できる(〇・×)
〇の数 個 ×の数 個
A、B、Cと各項目がありますが、〇の数が一番多い項目はどの項目ですか?
各項目の〇の数がほかの項目に比べて多い項目で、コミュニケーションタイプが別れます。
Aの項目で〇の数が多かった方
・攻撃的自己表現タイプ(アグレッシブタイプ)
表現の仕方として、自分の欲求を通す、相手に命令する、大声で怒鳴る、相手を操作する、一見すると自分の言いたいことは言えているように思いますが、攻撃的表現をされた側は傷つき、萎縮し、攻撃的人物から離れていく事になります。
その結果、主張を通したものの、後味の悪い気分になり最終的には孤立することになります。
Bの項目で〇の数が多かった方
・非主張的自己表現タイプ(ノンアサーティブタイプ)
自分の考えや主張を表現することなく相手に合わせる、自分に自信がなく本意でなくて
も相手の主張を受け入れるので、ストレスを感じやすい。
このタイプは、言いたいことがあるのに自分の意見や気持ちを言わず、言い出せない人が多く言ったところで相手に伝わりにくい傾向があります。
非自己表現的表現を続けていると、相手から「なんでも言うことを聞いてくれる都合のいい人」と思われてしまいます。
それが加速すると、本来はしたくない役割を任されたり都合よく利用されたりします。
Cの項目で〇の数が多かった方
・アサーティブ自己表現タイプ(アサーティブタイプ)
相手の気持ちや受け止め方に配慮しながら自分の考えや主張を相手に伝える
相手と意見が対立した時でも誠実に対話することでお互いの妥協点を探り問題解決を目指す。相手が苦手なタイプでも論理的に話をすることができる
ご自身のコミュニケーションタイプはわかりましたか?
もう少しわかりやすく例えるなら、国民的アニメ、ドラえもんのキャラクターで例える
ことができますのでご紹介します。
アグレッシブタイプ→ジャイアン
ノンアサーティブタイプ→のび太君
アサーティブタイプ→しずかちゃん
各キャラクターがどんな人物かはみなさまご存じかと思いますので省かせてもらいます。
最後は2人1組になり、言葉だけで説明された絵をどれだけ正確に書けるか伝言ゲーム
を行いました。
最後は2人1組になり、言葉だけで説明された絵をどれだけ正確に書けるか伝言ゲーム
を行いました。
絵の線がはっきりしているほうが答えですが、いかに言葉をうまく伝えるか、情報を聞
き出すか、情報を送る、受け取るためのコミュニケーション能力が重要だと実感しまし
た。
ここまでお付き合いくださりありがとうございます。
こんな感じで勉強会も理解しやすさを求めて飽きないように考えながら実施しています。
みなさまにも楽しさが伝わればうれしいです。
緊急時対応の勉強会
2020年10月27日
緊急時対応の勉強会
令和2年9月28日(月)
今回の苑内研修は急変時の対応です。
高齢者施設において、様々な疾患をお持ちの利用者様が急変することは珍しくはありません。
その時にどのように対応するべきか、またしなければならないのかを
再確認の意味と知識の向上のために開催しました。
今回の内容は医療が専門になりますので、講師は看護師にお願いしました。
講義方式ではなく、実践方式で行ってもらいました。


いざ大事な時に何も知らない、何もできないとなると、生命にかかわってきますので
手順を追って説明し、体験することで学習します。
次は、緊急時に必要になる色々な器具の説明です。

普段、見慣れないものばかりでどのような時に使用するのかまた、用意するのか
説明をうけました。
私たちは、生命をお預かりしています。
そのことを肝に銘じて日々のケアを行っています。
ここまで目を通していただきありがとうございます。
令和2年9月28日(月)
今回の苑内研修は急変時の対応です。
高齢者施設において、様々な疾患をお持ちの利用者様が急変することは珍しくはありません。
その時にどのように対応するべきか、またしなければならないのかを
再確認の意味と知識の向上のために開催しました。
今回の内容は医療が専門になりますので、講師は看護師にお願いしました。
講義方式ではなく、実践方式で行ってもらいました。
いざ大事な時に何も知らない、何もできないとなると、生命にかかわってきますので
手順を追って説明し、体験することで学習します。
次は、緊急時に必要になる色々な器具の説明です。
普段、見慣れないものばかりでどのような時に使用するのかまた、用意するのか
説明をうけました。
私たちは、生命をお預かりしています。
そのことを肝に銘じて日々のケアを行っています。
ここまで目を通していただきありがとうございます。
高齢者虐待について
2020年10月09日
高齢者虐待について
令和2年8月24日(月)
今回は8月24日に開催されました、高齢者虐待についての勉強会をご紹介します。
高齢者虐待ってどんなイメージをお持ちでしょうか? 単に虐待と言っいてもいくつかの種類に分かれています。 簡単にご紹介します。
・身体的虐待 身体に外傷が生じる又は、恐れのある暴力行為
・ネグレクト 介護、世話の放棄・放任
・心理的虐待 暴言もしくは、拒否的な対応で心理的外傷を与える言動
・性的虐待 わいせつな行為をする事、させる事
・経済的虐待 本人の合意なしに金銭や、財産を使用する事。
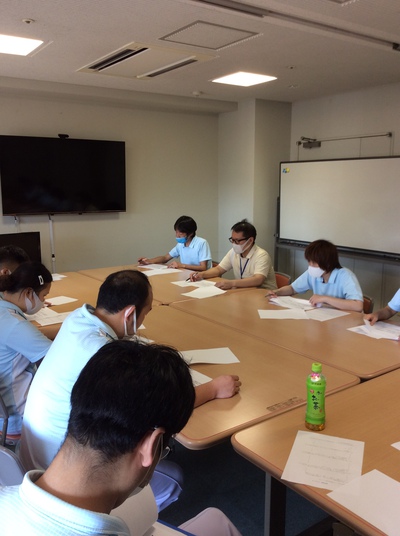
上記の5つの項目が高齢者虐待防止法に定められています。
虐待に含まれる項目に、身体拘束と言う言葉がございます。
簡単にご紹介すると、「緊急時や、やむえない場合」を除き、高齢者の生命や体を保護するための措置とされています。
では、「緊急時や、やむえない場合」とはどんな時でしょう? 簡単にご紹介しますと
・生命または身体が危険性にさらされる可能性が著しく高い(切迫性)
・身体拘束や、行動の制限を行う以外に介護方法がない(非代替性)
・身体拘束や、行動の制限を一時的に行う (一時性)
以上、3つの項目に該当する場合を「緊急時や、やむえない場合」とし、身体拘束へのプロセスを考えていきます。

身体拘束の具体的な例えをするならば
・徘徊しないように、転落しないように車椅子、ベッドに手足をヒモ等で縛る
・ベッドから降りられないようにベッド柵で囲む
・点滴のチューブを引き抜かない、皮膚を掻きむしらないようにミトン型の手袋をつける
・立ち上がる能力がある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
など、様々な行為がございます。
上でもご紹介しましたが、大阪府の指針に「緊急時や、やむえない場合」の身体拘束を考えるためのプロセスがありますので少しご紹介します。
・「緊急時や、やむえない場合」の判断は、担当職員個人またはチームではなく、施設全体で考える。
・考えるために、関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断する体制を原則とする。
・身体拘束の内容、理由、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、理解を求めることが必要である。
・常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合は、直ちに解除する。
・身体拘束の態様、時間、身心、の状況や「緊急時や、やむえない場合」の理由を記録することが必要である。
(※大阪府の身体拘束ゼロ推進標準マニュアルから引用)
ここまで身体拘束や、高齢者虐待についてご紹介しましたが、ここ雅秀苑では
月1回の委員会を開催し、各職種への身体拘束や高齢者虐待についての実態状況の確認や勉強会等を開催し、
高齢者虐待、身体拘束は行わないとしています。
今後も、利用者様に安心で、快適で、安全な生活空間を提供できるように職員一同
がんばってまいりますので応援、よろしくお願いします。
令和2年8月24日(月)
今回は8月24日に開催されました、高齢者虐待についての勉強会をご紹介します。
高齢者虐待ってどんなイメージをお持ちでしょうか? 単に虐待と言っいてもいくつかの種類に分かれています。 簡単にご紹介します。
・身体的虐待 身体に外傷が生じる又は、恐れのある暴力行為
・ネグレクト 介護、世話の放棄・放任
・心理的虐待 暴言もしくは、拒否的な対応で心理的外傷を与える言動
・性的虐待 わいせつな行為をする事、させる事
・経済的虐待 本人の合意なしに金銭や、財産を使用する事。
上記の5つの項目が高齢者虐待防止法に定められています。
虐待に含まれる項目に、身体拘束と言う言葉がございます。
簡単にご紹介すると、「緊急時や、やむえない場合」を除き、高齢者の生命や体を保護するための措置とされています。
では、「緊急時や、やむえない場合」とはどんな時でしょう? 簡単にご紹介しますと
・生命または身体が危険性にさらされる可能性が著しく高い(切迫性)
・身体拘束や、行動の制限を行う以外に介護方法がない(非代替性)
・身体拘束や、行動の制限を一時的に行う (一時性)
以上、3つの項目に該当する場合を「緊急時や、やむえない場合」とし、身体拘束へのプロセスを考えていきます。
身体拘束の具体的な例えをするならば
・徘徊しないように、転落しないように車椅子、ベッドに手足をヒモ等で縛る
・ベッドから降りられないようにベッド柵で囲む
・点滴のチューブを引き抜かない、皮膚を掻きむしらないようにミトン型の手袋をつける
・立ち上がる能力がある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
・行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
など、様々な行為がございます。
上でもご紹介しましたが、大阪府の指針に「緊急時や、やむえない場合」の身体拘束を考えるためのプロセスがありますので少しご紹介します。
・「緊急時や、やむえない場合」の判断は、担当職員個人またはチームではなく、施設全体で考える。
・考えるために、関係者が幅広く参加したカンファレンスで判断する体制を原則とする。
・身体拘束の内容、理由、時間、期間などを高齢者本人や家族に対して十分に説明し、理解を求めることが必要である。
・常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合は、直ちに解除する。
・身体拘束の態様、時間、身心、の状況や「緊急時や、やむえない場合」の理由を記録することが必要である。
(※大阪府の身体拘束ゼロ推進標準マニュアルから引用)
ここまで身体拘束や、高齢者虐待についてご紹介しましたが、ここ雅秀苑では
月1回の委員会を開催し、各職種への身体拘束や高齢者虐待についての実態状況の確認や勉強会等を開催し、
高齢者虐待、身体拘束は行わないとしています。
今後も、利用者様に安心で、快適で、安全な生活空間を提供できるように職員一同
がんばってまいりますので応援、よろしくお願いします。
利用者様との接し方
2020年10月09日
利用者様との接し方
令和2年8月20日
本日は利用者様との接し方と題しまして、接遇の勉強会を開催しました。


まずは、高齢者の特徴ってどんなことだろう?について考えてもらいました。
みなさん、高齢者の特徴ってどんな事だと思いますか?
高齢者の特徴としまして
・運動機能、筋力の低下(廃用症候群になりやすい)
・脱水症になりやすい
・便秘になりやすい
・加齢に伴う疾患や慢性疾患をもっている
・皮膚が弱い
・骨折や内出血になりやすい
などが特徴としてあげられると思います。
上にあげられている事はすべて加齢に伴う高齢者の特徴としてみられます。
高齢者の特徴がわかれば、どのように高齢者と接したら良いのかが見えてくると思います。
次は、高齢者の特徴がわかったうえで、どう接するかを考えてみました。
・思いやりをもつ
・優しく触れる
・自分がされて嫌なことはしない
・ユマニチュードの技法を使用する(認知症の人との接する技法)
・ノーリフトケアの実践(利用者様を抱え上げない様にするための介護の技術)
等々、色々と意見がでてきました。
高齢者の特徴が理解できると接し方がわかりやすなりました。
いよいよ次は利用者様になりきって介助を受けてみてどんな介助をされると不快になるのか
安楽になるのかを実際に肌で感じてもらい実感してもらいました。


普段、職員は自分自身が介助を受けることがない為、介助される側になりきって利用者様の体験をしてもらうと「わきの下に手を入れられると、気持ちが悪かった」「肩に手を回すと楽に感じたよ」など
触れる位置一つで不快になる事が実感できました。
今までやってきた介助にひと工夫を付け加えることで、よりよいケアができることの再認識につながりました。
我々職員は、利用者様に安心、安楽、安全をどう提供できるか日々考え、学び、知識として備え利用者様に還元できるように実践しています。
これからも努力を怠らず、利用者様を笑顔にできるよう努めてまいります。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
皆様におかれましては、コロナウイルスなどに感染しないよう、負けないよう、職員一同心より願っております。
令和2年8月20日
本日は利用者様との接し方と題しまして、接遇の勉強会を開催しました。
まずは、高齢者の特徴ってどんなことだろう?について考えてもらいました。
みなさん、高齢者の特徴ってどんな事だと思いますか?
高齢者の特徴としまして
・運動機能、筋力の低下(廃用症候群になりやすい)
・脱水症になりやすい
・便秘になりやすい
・加齢に伴う疾患や慢性疾患をもっている
・皮膚が弱い
・骨折や内出血になりやすい
などが特徴としてあげられると思います。
上にあげられている事はすべて加齢に伴う高齢者の特徴としてみられます。
高齢者の特徴がわかれば、どのように高齢者と接したら良いのかが見えてくると思います。
次は、高齢者の特徴がわかったうえで、どう接するかを考えてみました。
・思いやりをもつ
・優しく触れる
・自分がされて嫌なことはしない
・ユマニチュードの技法を使用する(認知症の人との接する技法)
・ノーリフトケアの実践(利用者様を抱え上げない様にするための介護の技術)
等々、色々と意見がでてきました。
高齢者の特徴が理解できると接し方がわかりやすなりました。
いよいよ次は利用者様になりきって介助を受けてみてどんな介助をされると不快になるのか
安楽になるのかを実際に肌で感じてもらい実感してもらいました。
普段、職員は自分自身が介助を受けることがない為、介助される側になりきって利用者様の体験をしてもらうと「わきの下に手を入れられると、気持ちが悪かった」「肩に手を回すと楽に感じたよ」など
触れる位置一つで不快になる事が実感できました。
今までやってきた介助にひと工夫を付け加えることで、よりよいケアができることの再認識につながりました。
我々職員は、利用者様に安心、安楽、安全をどう提供できるか日々考え、学び、知識として備え利用者様に還元できるように実践しています。
これからも努力を怠らず、利用者様を笑顔にできるよう努めてまいります。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
皆様におかれましては、コロナウイルスなどに感染しないよう、負けないよう、職員一同心より願っております。
★スイカ割り★
2020年10月09日
★スイカ割り★
雅秀苑では、毎年恒例のスイカ割りを開催しました~!!
夏の風物詩ですね


目隠しをしているのでなかなかスイカに当たらず
皆様苦戦されていた中、4人目の挑戦です。

皆様の誘導もありやっとの思いでスイカの前に到着し、
「せーの!えいっ!!!」の合図で棒を振り下ろします

パチンっ!と大きな音とともにスイカが割れました!!
さすが、男性です。力強い一本でした!
無事にスイカは割れたのですが
最後におまけで職員に目隠しで棒の周りを10周回った後にスイカを割ってもらいました。

スイカ割りへの意気込みを語り皆様が見守る中、スタートしましたが

10周回り切れず
コテっ、、、皆様大爆笑でした。笑

皆様の応援あって何とか持ち直し
無事にスイカの前まで到着出来ました☆
※感染予防のため、スイカはビニール袋に入れており
雅秀苑では感染に常に注意しレクリエーションに取り組んでいます。
割ったスイカは皆様で分けて食べていただきました。
次回のレクレーションも楽しみです☆
雅秀苑では、毎年恒例のスイカ割りを開催しました~!!
夏の風物詩ですね



目隠しをしているのでなかなかスイカに当たらず
皆様苦戦されていた中、4人目の挑戦です。


皆様の誘導もありやっとの思いでスイカの前に到着し、
「せーの!えいっ!!!」の合図で棒を振り下ろします

パチンっ!と大きな音とともにスイカが割れました!!
さすが、男性です。力強い一本でした!
無事にスイカは割れたのですが
最後におまけで職員に目隠しで棒の周りを10周回った後にスイカを割ってもらいました。


スイカ割りへの意気込みを語り皆様が見守る中、スタートしましたが

10周回り切れず
コテっ、、、皆様大爆笑でした。笑

皆様の応援あって何とか持ち直し
無事にスイカの前まで到着出来ました☆
※感染予防のため、スイカはビニール袋に入れており
雅秀苑では感染に常に注意しレクリエーションに取り組んでいます。
割ったスイカは皆様で分けて食べていただきました。
次回のレクレーションも楽しみです☆
★夏の行事食★
2020年09月10日
 夏の行事食
夏の行事食
☆山の日☆

比較的新しい国民の祝日として設定された『山の日』ですが、本来は毎年8月11日に決められていましたが、今年はオリンピックyearということで、オリンピックの閉会式の翌日に合わせて8月10日(月)に変更されていました。残念ながらオリンピックは延期になりましたね

苑では、行事食として『枝豆ごはん、天ぷらの盛り合わせ、焼き茄子、赤だし、スイカ』を提供させていただきました。天ぷらは人気メニューの1つなので喜んでいただきました。
 デイケアおやつレク
デイケアおやつレク
☆たこ焼き☆


今年は、毎年恒例の夏祭りができなかったのですが、少しでも雰囲気を楽しんでいただきたいということで、8月のおやつレクは“たこ焼き”を実施しました。
職員一同心を込めて焼き上げました。
クルクル、クルクル…できがあり

アツアツで美味しいうちに食べていただきました。
☆ところてん☆


今年も記録的猛暑が続き、9月になっても暑い日が続いていますね。
デイケアでは、9月のおやつレクは“ところてん”を実施しました。
甘い味付けが好きであったり、酢っぱい味付けが好きであったりと、好みが違うと思いますので、『黒蜜きなこ』と『ふりかけ&黒酢』のどちらかをチョイスできるようにしました。
個人的には甘党なので、黒蜜きなこが好きですが、黒酢を選択される方も多かったです。
この時期は、さっぱりと食べられる物が好まれるようですね

☆カラオケ大会☆
2020年09月04日
毎年、全階の利用者様に集まって頂き、カラオケ大会 を開催していましたが、今年はコロナウイルス感染予防の為、各階ごとに行ないました。
を開催していましたが、今年はコロナウイルス感染予防の為、各階ごとに行ないました。
各階では、換気に配慮して、歌唱される利用者様と聴席の距離、聴席と聴席の間隔を十分に離しました。
当日のスタッフや参加者に検温を実地、手の消毒を行ないました。
マイクは一人が歌い終われば、その都度消毒を行ないました。


合いの手は止めて、タンブリンやマラカスなどを使用して応援するようにしました。
また、感染予防ばかりではなく、ステージの飾りつけや歌唱される利用者様にチョーネクタイを手作りして付けてもらいました。
いつもと違う雰囲気の中で楽しめるか心配でしたが、熱唱される利用者様や笑顔で応援されている利用者様の姿を見て安心しました。
早くコロナが落ち着き、利用者様の歌声や笑顔を、ご家族様にも聴いて見て頂けたらと思いました。
今後もご利用者の方々に喜んでいただけるような行事を考えて参ります。
 を開催していましたが、今年はコロナウイルス感染予防の為、各階ごとに行ないました。
を開催していましたが、今年はコロナウイルス感染予防の為、各階ごとに行ないました。
各階では、換気に配慮して、歌唱される利用者様と聴席の距離、聴席と聴席の間隔を十分に離しました。

当日のスタッフや参加者に検温を実地、手の消毒を行ないました。

マイクは一人が歌い終われば、その都度消毒を行ないました。

合いの手は止めて、タンブリンやマラカスなどを使用して応援するようにしました。

また、感染予防ばかりではなく、ステージの飾りつけや歌唱される利用者様にチョーネクタイを手作りして付けてもらいました。

いつもと違う雰囲気の中で楽しめるか心配でしたが、熱唱される利用者様や笑顔で応援されている利用者様の姿を見て安心しました。

早くコロナが落ち着き、利用者様の歌声や笑顔を、ご家族様にも聴いて見て頂けたらと思いました。

今後もご利用者の方々に喜んでいただけるような行事を考えて参ります。

★七夕レク★
2020年09月04日
7月といえば七夕ですね。
七夕は、織姫と彦星が一年に一度、天の川を渡って再会するというエピソードが有名ですね。
そんな七夕に向けて、雅秀苑では事前に皆様に短冊と飾りつけを作って頂きました。
短冊には「家族が元気に過ごせますように」「世界平和」「健康第一」など健康や平和祈願の願い事が多かったです。
素敵な短冊も無事に完成し、各フロアで七夕レクを実施しました。
浴衣を着て盛り上げてくれる介護職員もいました!
そのあとは皆様で「たなばたさま」を歌いました。
いつ聴いても、懐かしい気持ちになります。
最後に皆様の短冊の願い事を発表しました。
ユニークな願い事もあり笑いを誘いました。
ご家族様にもお願いし、作って頂いた短冊も一緒に発表しました。
家族様の短冊を読み上げると利用者様は嬉しそうにしておられました。
利用者様の願い事、職員の願い事、皆様の願い事が叶いますように☆
雅秀苑の職員は七夕に織姫と彦星が天の川で出会えたように、利用者様とご家族様が面会できる日が一日でも早く訪れることを願っています。

七夕は、織姫と彦星が一年に一度、天の川を渡って再会するというエピソードが有名ですね。

そんな七夕に向けて、雅秀苑では事前に皆様に短冊と飾りつけを作って頂きました。

短冊には「家族が元気に過ごせますように」「世界平和」「健康第一」など健康や平和祈願の願い事が多かったです。

素敵な短冊も無事に完成し、各フロアで七夕レクを実施しました。

浴衣を着て盛り上げてくれる介護職員もいました!

そのあとは皆様で「たなばたさま」を歌いました。

いつ聴いても、懐かしい気持ちになります。

最後に皆様の短冊の願い事を発表しました。

ユニークな願い事もあり笑いを誘いました。

ご家族様にもお願いし、作って頂いた短冊も一緒に発表しました。

家族様の短冊を読み上げると利用者様は嬉しそうにしておられました。

利用者様の願い事、職員の願い事、皆様の願い事が叶いますように☆

雅秀苑の職員は七夕に織姫と彦星が天の川で出会えたように、利用者様とご家族様が面会できる日が一日でも早く訪れることを願っています。

☆認知症ケアについて☆
2020年09月04日
認知症ケアについて
7/8に認知症ケアについて苑内研修を行いました。
少しずつではありますが「質の良いケアの提供」を目指し学べる環境ができてきました。

さて、認知症と言えば皆さんどのようなイメージをお持ちですか?から始まり…。
ユマニチュードって聞いた事はありますか?
<ユマニチュードとは>
知的・感情・言語による包括的コミュニケーションに基づいた技法です。
<ユマニチュードが目指すこと>
ユマニチュードは「人とは何か」「ケアをする人とは何か」を問う哲学と、それに基づく実践的な技術から成り立っています。
①この技法の特徴は、ケアの対象となる人の「人間らしさ」を尊重し続けること。
②ケアする人はケアを受ける人にたとえ反応がなくても「あなたを大切に思っています」
「あなたはここにいますよ」というメッセージを発信し続けます。
③具体的には「見る」「話す」「触れる」「立つ」という人間的の特徴に働きかけ、ケアを
受ける人に「自分は人間である」ということを思い出して頂く
④ケアを通じて、言葉によるコミュニケーションが難しい人とポジティブな関係を築いていく
難しそうで簡単? 簡単そうで難しいのが認知症ケア。学べば学ぶほど底がない介護の世界。
簡単そうで難しいのが認知症ケア。学べば学ぶほど底がない介護の世界。
私たちもまだまだ勉強不足です…. だからこそ勉強あるのみ。
だからこそ勉強あるのみ。

続いて~
認知症高齢者の視界の広さってどの程度?トイレットペーパーの芯を目に当てて覗いてみてください。
そこに後ろや横から声を掛けられたら!?
職員からは…。
「全然見えない」「怖い」「声は聞こえるけど急に顔が出てくるとびっくりする」「ドキッとして怒る」という声がでました。
もしかすると叩かれたりすることは高齢者の方の防衛本能ではないでしょうか…。
こんな時、水平に目を合わせて正面から顔を近づけて見つめる時間を長くとってみて下さい。
これがユマニチュードで言う「見る」です。そのあとに優しく話しかける…。
試してみて下さい。
まだまだ勉強会の内容を書きたいところですが、かなーーーーーり長くなるので
この辺りにしておきます(笑)。講義あり、体験ありと充実した1時間でした。
次回の研修会もお楽しみに~!!
7/8に認知症ケアについて苑内研修を行いました。

少しずつではありますが「質の良いケアの提供」を目指し学べる環境ができてきました。

さて、認知症と言えば皆さんどのようなイメージをお持ちですか?から始まり…。
ユマニチュードって聞いた事はありますか?

<ユマニチュードとは>
知的・感情・言語による包括的コミュニケーションに基づいた技法です。
<ユマニチュードが目指すこと>
ユマニチュードは「人とは何か」「ケアをする人とは何か」を問う哲学と、それに基づく実践的な技術から成り立っています。
①この技法の特徴は、ケアの対象となる人の「人間らしさ」を尊重し続けること。
②ケアする人はケアを受ける人にたとえ反応がなくても「あなたを大切に思っています」
「あなたはここにいますよ」というメッセージを発信し続けます。
③具体的には「見る」「話す」「触れる」「立つ」という人間的の特徴に働きかけ、ケアを
受ける人に「自分は人間である」ということを思い出して頂く
④ケアを通じて、言葉によるコミュニケーションが難しい人とポジティブな関係を築いていく
難しそうで簡単?
 簡単そうで難しいのが認知症ケア。学べば学ぶほど底がない介護の世界。
簡単そうで難しいのが認知症ケア。学べば学ぶほど底がない介護の世界。
私たちもまだまだ勉強不足です….
 だからこそ勉強あるのみ。
だからこそ勉強あるのみ。
続いて~
認知症高齢者の視界の広さってどの程度?トイレットペーパーの芯を目に当てて覗いてみてください。

そこに後ろや横から声を掛けられたら!?

職員からは…。
「全然見えない」「怖い」「声は聞こえるけど急に顔が出てくるとびっくりする」「ドキッとして怒る」という声がでました。

もしかすると叩かれたりすることは高齢者の方の防衛本能ではないでしょうか…。

こんな時、水平に目を合わせて正面から顔を近づけて見つめる時間を長くとってみて下さい。

これがユマニチュードで言う「見る」です。そのあとに優しく話しかける…。

試してみて下さい。

まだまだ勉強会の内容を書きたいところですが、かなーーーーーり長くなるので

この辺りにしておきます(笑)。講義あり、体験ありと充実した1時間でした。

次回の研修会もお楽しみに~!!

雅秀苑 部署紹介 ~リハビリテーション~
2020年09月04日
ブログをご閲覧のみなさん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。
雅秀苑リハビリテーション部です。
リハビリテーション部には機能訓練指導員として、理学療法士(PT)常勤13名、作業療法士(OT)常勤1名、計13名(男性5:女性9)のセラピストが利用者さまへリハビリテーションを実施しています。
現在リハビリテーション部では
他部門との連携を強化しながら、ノーリフトケアに取り組んでいます。
今回のブログでは、私たちの役割をお話しさせていただきます。
私たち機能訓練指導員は、1人で動くことが難しい、不安がある、といった利用者様に寄り添い、
寝返りや起き上がり・車椅子やベッドへの移乗・歩行・トイレ動作などのADL(日常生活活動)の向上をサポートする為、利用者様に訓練や指導を実施します。
単に”マッサージをする人”といったイメージをもたれておられる方もいらっしゃることかと思われますが、
実際には主として運動をすることで”動きやすい身体作り”をお手伝いすることが目的です。
リハビリテーション時間以外での日常生活動作を指導、生活不活発病を予防する為の自主的な訓練も指導することで、できる限り利用者様の生活範囲を拡大できるようにサポートさせていただきますので、”やりたい動作”や”やってみたい運動”などありましたらご相談ください。
利用者様だけでなく、家族様も利用者様への介助方法や、リハビリテーションのこと、普段の生活動作の中で困っていることなど、お気軽にご質問・ご相談ください。


雅秀苑リハビリテーション部です。

リハビリテーション部には機能訓練指導員として、理学療法士(PT)常勤13名、作業療法士(OT)常勤1名、計13名(男性5:女性9)のセラピストが利用者さまへリハビリテーションを実施しています。
現在リハビリテーション部では
他部門との連携を強化しながら、ノーリフトケアに取り組んでいます。

今回のブログでは、私たちの役割をお話しさせていただきます。

私たち機能訓練指導員は、1人で動くことが難しい、不安がある、といった利用者様に寄り添い、
寝返りや起き上がり・車椅子やベッドへの移乗・歩行・トイレ動作などのADL(日常生活活動)の向上をサポートする為、利用者様に訓練や指導を実施します。

単に”マッサージをする人”といったイメージをもたれておられる方もいらっしゃることかと思われますが、
実際には主として運動をすることで”動きやすい身体作り”をお手伝いすることが目的です。

リハビリテーション時間以外での日常生活動作を指導、生活不活発病を予防する為の自主的な訓練も指導することで、できる限り利用者様の生活範囲を拡大できるようにサポートさせていただきますので、”やりたい動作”や”やってみたい運動”などありましたらご相談ください。

利用者様だけでなく、家族様も利用者様への介助方法や、リハビリテーションのこと、普段の生活動作の中で困っていることなど、お気軽にご質問・ご相談ください。


- 施設長挨拶
- お知らせ(新着情報)
- 行事風景
- お食事について
- 各種職場からの挨拶
- サービス案内
- 手続き案内
- リハビリ科のご案内
- 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション
- 交通案内
- お問い合せ
- 施設概要
- 難波福祉会について
介護老人保健施設 雅秀苑
大阪市住之江区南港北1-4-1TEL:06-6613-8501
最近の記事
雅秀苑(入所)空床情報のお知らせ(R7.5.15) (5/15)
お花見 散歩 (5/15)
雅秀苑(入所)空床情報のお知らせ(R7.4.30) (4/30)
雅秀苑(入所)空床情報のお知らせ(R7.4.15) (4/15)
たこ焼きレクのご様子 (4/11)
たこやきレク 工程 (4/11)
雅秀苑(入所)空床情報のお知らせ(R7.3.31) (3/31)
BCP防災訓練 更新~♬ (3/19)